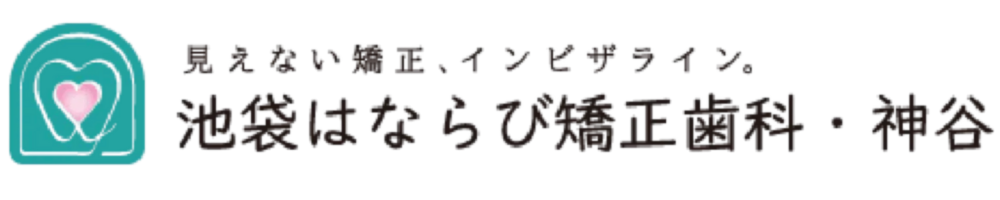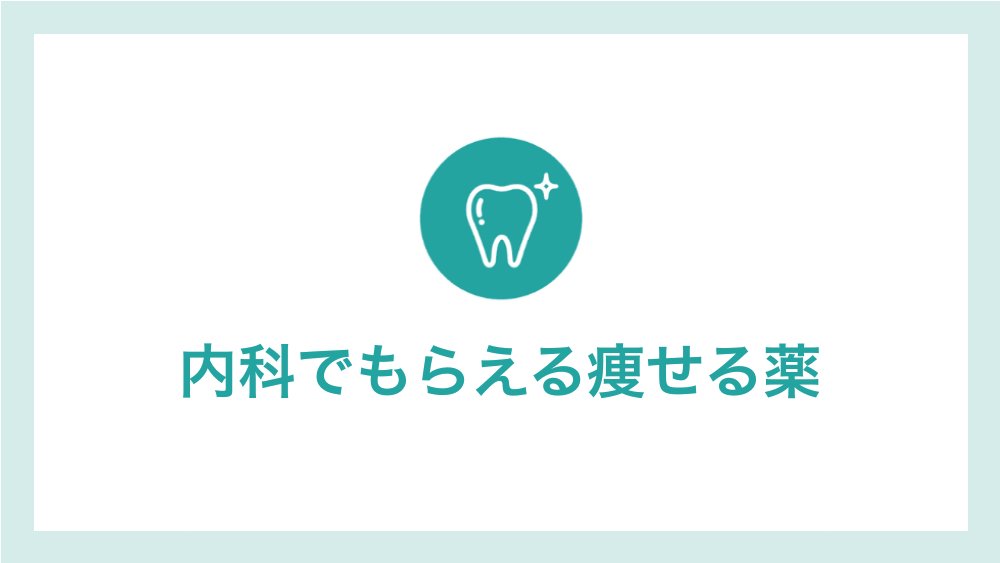「何をやっても痩せない」「ダイエットの効果が全然出ない」という人でも、メディカルダイエットで医師の力を借りて痩せることが可能です。
この記事では「内科でもらえる痩せる薬や効果、保険適用の有無」をお伝えしていきます。
なお、とにかく痩せたいと考えている人は、GLP-1ダイエットがおすすめです。
芸能人やインフルエンサーも使用している薬で、オンライン診療で処方してもらうことができます。
マンジャロやリベルサスを処方しているオンラインクリニックの中でも、特におすすめの3院を以下の表にまとめました。
| クリニック名 | 特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|
 クリニックフォア | 診療実績は700万件以上突破※ 2週間のトライアルプランは4,378円(税込) 薬は最短翌日到着&全国配送可能※1 | 公式サイト |
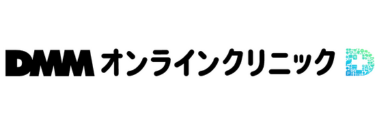 DMMオンラインクリニック | クーポン適用で最大5,000円オフで始められる 診察料・再診料ともに無料 最短当日発送ですぐ受け取れる | 公式サイト |
 デジタルクリニック | 初診料0円・お薬代1,000円オフで始められる 約10万件の治療実績があり信頼性が高い LINEで医療ダイエットのおすすめ度をチェックできる | 公式サイト |
注釈
※2020年4月~2025年8月当クリニックのオンライン診療実績(お薬の発送実績込み。発送集約時は集約前の発送回数に転換して計算)
※1 診療時間・決済完了時間・お届け先エリアによって異なります。
内科でもらえる痩せる薬

内科でもらえる痩せる薬は、以下の通りです。
| 内科でもらえる痩せる薬 |
|---|
| GLP‑1受容体作動薬 SGLT2阻害薬 食欲抑制薬 漢方薬 脂肪吸収抑制薬 |
それぞれ解説します。
GLP‑1受容体作動薬
GLP‑1受容体作動薬は、週1回の自己注射だけで食欲を緩やかに抑え、月平均3〜7kgの体重減少を目指せる薬です。
注射後は胃の動きが遅くなり、満腹感が長く続くため、間食や大盛りを自然に控えられます。
使用しているインフルエンサーや芸能人も多く、楽に理想的な見た目を目指すことができます。
しかし、投与初期に吐き気や下痢が生じることがあるため、医師は開始用量を2.5mgに設定し4週間かけて段階的に増量します。
| 料金相場 | 自費診療:月3万〜7万円 保険適用時:月1万5千円前後 |
|---|---|
| 効果 | 血糖値の上昇に応じてインスリン分泌を促進し、胃排出遅延や食欲抑制により体重減少 |
| 主な副作用 | 悪心・嘔吐 下痢または便秘 低血糖 など |
| 保険適用の条件 | 2型糖尿病の治療目的で、食事・運動療法や他剤で効果不十分な場合 |
SGLT2阻害薬
SGLT2阻害薬は、腎臓での糖再吸収を抑え尿とともにおよそ250kcalを排泄させる仕組みにより、穏やかな減量効果を得られます。
価格が保険3割負担で月1,500円前後と比較的安価なため、血糖管理と体重コントロールを同時に望む人に選ばれています。
ただし、脱水や尿路感染症を防ぐには水分摂取を普段より意識する必要があります。
| 料金相場 | 保険3割負担:月1,500円前後 自費処方:月4,000〜7,000円 定期的な尿ケトン検査費用が別途 |
|---|---|
| 効果 | 腎臓でのブドウ糖再吸収を阻害し、尿中に糖を排泄することで血糖値と体重を低下させる |
| 主な副作用 | 尿路・性器感染症 脱水・口渇 ケトアシドーシス(まれ) |
| 保険適用の条件 | 2型糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(CKD)などの治療に使用可能 |
食欲抑制薬
サノレックスなどの食欲抑制薬は、脳の満腹中枢に作用し食べ物を思い出す回数そのものを減らしてくれます。
そのため、短期間でエネルギー摂取量を大きく下げられます。
厚生労働省によると、3か月の連続服用で平均5%の体重減少が見込めますが、使用は連続3か月までに制限されています。
不眠や動悸など交感神経の刺激症状が出やすいため、夕方以降の服用は避けけましょう。
また、保険適用はBMI35以上など厳しい条件に限られるので、多くのクリニックでは自費扱いとなります。
| 料金相場 | 自費:1錠300円・月1〜2万円 BMI35以上なら保険適用で月3,000円台 連続服用は最長3か月 |
|---|---|
| 効果 | 中枢神経系に作用し食欲を抑制することで摂取カロリーを減らす |
| 主な副作用 | 不眠・口渇 動悸・血圧上昇 依存性リスク |
| 保険適用の条件 | 高度肥満(BMI35以上)かつ減量治療の一環として医師の管理下で使用、原則12週間まで |
漢方薬
防風通聖散をはじめとする漢方薬は、脂質代謝を促し便通を整えることで体内の余分な水分と老廃物を排出し、ウエスト周りの軽減につながります。
医療用エキス製剤は保険診療で1日あたり30〜50円程度と手頃ですが、同じ処方でも市販薬は自費で数倍の価格になる場合があります。
また、効果は穏やかで、厚生労働省の調査では3か月で1〜2kgの減量にとどまる例が多く、食事や運動の調整を並行させる必要があります。
カリウム保持性が高いため、高血圧治療薬を服用中の人は低カリウム血症にならないよう定期的な血液検査を受ける必要があります。
| 料金相場 | 保険適用:1日約40円 市販薬:月3,000〜6,000円 煎じ薬は調剤費が加算 |
|---|---|
| 効果 | 体質や症状に応じて代謝促進・便通改善・水分代謝の調整などを通じて減量を補助 |
| 主な副作用 | 偽アルドステロン症 肝機能障害 発疹 |
| 保険適用の条件 | 肥満症に伴う便秘や高血圧などに限り、診療報酬上保険適用となる |
脂肪吸収抑制薬
オルリスタットなどの脂肪吸収抑制薬は、小腸のリパーゼを30%ほど阻害してくれます。
結果的に、食事由来の脂肪をそのまま排泄させることで、2〜4kgの体重減少が期待されています。
処方薬としては国内未承認のため、都内の一部クリニックでは個人輸入代行を活用して1カ月分約1.5万円で提供しています。
服用中は油分を多く含む食事で脂肪便が起こりやすく、下着の汚染を避けるために脂肪摂取量を全体の30%未満に抑える食事計画が薦められます。
| 料金相場 | 自費:月約1.5万円 個人輸入の送料が別途 ビタミンサプリ併用費用を要する |
|---|---|
| 効果 | 腸内のリパーゼを阻害して脂肪の吸収を抑え、摂取カロリーを減少させる |
| 主な副作用 | 脂肪便・腹部膨満 脂溶性ビタミン不足 便意切迫 |
| 保険適用の条件 | 日本国内では未承認のため保険適用外 |
内科でもらえる痩せる薬の効果

内科でもらえる痩せる薬には、以下のような効果があります。
| 内科でもらえる痩せる薬の効果 |
|---|
| 体重減少のメカニズム 合併症リスクの低減 見た目・QoL改善 |
それぞれ解説します。
体重減少のメカニズム
内科で処方される痩せる薬は、脳の食欲中枢を直接抑制して食事量を自然に減らすため、服用から約1週間で間食や大盛りを控えやすくなります。
特にGLP‑1受容体作動薬は、胃から腸への内容物の移動を遅らせ、食後の満腹感を長時間維持できます。
交感神経刺激薬マジンドールは基礎代謝を約5%上げるため、摂取カロリー減少と相乗し、体脂肪が減りやすくなります。
運動療法を併用すると筋量を保ちつつ脂肪が選択的に減るため、見た目が早期から変化し、モチベーション維持にも役立ちます。
合併症リスクの低減
体重を5%減らすと空腹時血糖が平均10mg/dL下がり、高血圧診断基準を満たす人の割合も約15%減ります。
その結果、薬物療法による減量は糖尿病や高血圧の発症を遅らせ、服用中の降圧薬や血糖降下薬を減量できる可能性も高まります。
さらに、肝機能異常の主因となる脂肪肝は10%の減量で肝脂肪が約30%減少すると報告され、将来の肝硬変リスクを抑えられます。
体重減少と代謝改善は相関するため、目標の半分しか減らなくても多くの場合で血糖や血圧の数値は先に改善します。
見た目・QOL改善
腹囲が10cm縮まると膝関節への荷重が歩行1歩当たり約4倍軽くなるため、立ち上がりや階段の上り下りが楽になり、日常の疲労感が減ります。
睡眠時無呼吸症候群は体重を10%減らすと無呼吸低呼吸指数が平均25%低下し、いびきや日中の眠気が目に見えて減ります。
皮下脂肪が薄くなることで首や顎のラインが際立ち、顔の印象が変わるため、自己肯定感が高まったという報告も少なくありません。
仕事や学業への集中力改善にも波及し、体力が付くことで運動習慣を続けやすい好循環が生まれます。
医学的な減量は外見の変化と同時に生活の質全体を底上げし、健康寿命を延ばす一助となります。
内科でもらえる痩せる薬の処方までの流れ

内科でもらえる痩せる薬の処方までの流れは、以下の通りです。
| 内科でもらえる痩せる薬の処方までの流れ |
|---|
| ステップ1:初診予約と問診 ステップ2:検査と診断 ステップ3:治療方針と薬の選択 ステップ4:定期フォローアップ |
それぞれ解説します。
ステップ1:初診予約と問診
薬を安全に使うため、BMIや既往歴を医師に正確に伝えることが欠かせません。
予約は電話やWEBで受け付ける医療機関が増えており、問診票を事前入力すると来院後の待ち時間が短縮されます。
問診では食事・運動・睡眠の状態に加え、市販サプリや過去の減量経験も確認されるため、服薬以外の改善策も整理できます。
虚血性心疾患や妊娠希望などの禁忌があれば薬ではなく生活指導中心に切り替わるため、情報を漏らさず伝えることが重要です。
ステップ2:検査と診断
採血や心電図で肝腎機能と心血管リスクを確認し、薬の適応と投与量を決めます。
血液検査では空腹時血糖、HbA1c、電解質に加え、膵酵素を測定して膵炎リスクを評価します。
腹部エコーで胆石が見つかった場合はGLP‑1系を避けるなど、画像所見も薬剤選択に直結します。
ステップ3:治療方針と薬の選択
医師はBMI、合併症、本人の希望を総合し、食欲抑制薬、SGLT2阻害薬、GLP‑1受容体作動薬などから1剤を提案します。
保険診療の対象はBMI35以上、またはBMI27以上で合併症がある場合に限られるため、それ以外の人は自由診療で費用を自己負担します。
費用の目安はマジンドール1か月分が約3千円、GLP‑1製剤が同期間約2万円、マンジャロが約4万円と幅があります。
薬は推奨最小用量から開始し、4週ごとに副作用と効果を見ながら漸増するのが一般的です。
ステップ4:定期フォローアップ
投与後1〜2か月ごとに体重と副作用を確認し、必要に応じて用量を調整すると効果と安全性を保ちやすくなります。
診察で血糖や血圧が改善していれば、内科治療中の薬を減量できる場合もあるため、最新の検査結果を持参しましょう。
目標体重に達した後も3〜6か月おきに受診し、再増量や副作用の早期発見に努めることで、長期的な減量維持が可能になります。
内科でもらえる痩せる薬を安全に使うポイント

内科でもらえる痩せる薬を安全に使うポイントは、以下の通りです。
| 内科でもらえる痩せる薬を安全に使うポイント |
|---|
| 医師の指示を守る 生活習慣の改善併用 副作用の早期対応 |
それぞれ解説します。
医師の指示を守る
医師から提示された用量と投与間隔を守ることで、体重減少効果を維持しつつ低血糖や胃腸障害を回避できます。
たとえば週1回のGLP‑1受容体作動薬なら、前回注射から最低5日を空けないと薬剤濃度が累積し、嘔吐が長引く危険が高まります。
さらに注射ペンは2〜8℃で冷蔵保管し、室温に2時間以上置くと薬効が低下すると添付文書に明記されているため、通勤時は保冷剤と一緒に携行すると品質を保ちやすいでしょう。
加えてリベルサス(経口セマグルチド)のように「起床直後に120mL以下の水で服用し、30分は飲食を控える」といった手順を守らないと、吸収率が十分に確保されません。
生活習慣の改善併用
食事と運動を同時に見直すと、薬だけでは平均10%前後にとどまる減量幅を15%以上に伸ばせると日本肥満学会の治療指針が示しています。
具体的には朝食後に20分の速歩を追加すると、GLP‑1作動薬の胃排出遅延作用で満腹感が高まり、夕食の摂取エネルギーが約300kcal減ったという研究結果があります。
さらに1日のたんぱく質量を体重1kgあたり1.2gへ増やすと、薬で急速に減る筋肉量を補え、基礎代謝の低下を抑えられるためリバウンドを防げます。
副作用の早期対応
気になる症状が出たら速やかに受診すると、重大な合併症への進展を抑えやすくなります。
GLP‑1系では悪心が17%、低血糖が12%ほど報告されており、制吐薬や食事調整を早めに行えば治療を継続しやすくなります。
もし激しい腹痛や背部痛が続けば膵炎を疑う必要があり、自己判断で休薬するより内科でアミラーゼ値を測定する方が安全です。
また注射部位に紅斑が広がった場合は細菌感染を疑い、24時間以内に抗菌薬を投与すると重症化を抑えられると厚労省の副作用情報に示されています。
内科でもらえる痩せる薬と市販薬・サプリの違い

内科でもらえる痩せる薬と市販薬・サプリの違いは、以下の通りです。
| 内科でもらえる痩せる薬と市販薬・サプリの違い |
|---|
| 効果の強さ 安全性と法規制 医療サポートの有無 |
それぞれ解説します。
効果の強さ
処方薬は体重の5〜15%の減量を目安に開発されていますが、市販サプリの多くは2〜3%にとどまります。
たとえばマンジャロ10mg群では68週後に平均‑15%の体重減少が確認された一方、茶カテキンサプリは‑2%程度にとどまったと学会誌が報告しています。
この差は、処方薬がホルモンや酵素を直接制御するのに対し、サプリは食品扱いで有効成分量や吸収率が限定的だからです。
安全性と法規制
処方薬は厚生労働省の審査を経て添付文書に用法と禁忌が示され、有害事象は定期的に再評価されます。
一方サプリは食品衛生法の枠組みで製造管理の基準が緩やかなため、有効成分のばらつきや重金属混入が指摘されたケースもあります。
また医師の処方箋が必要な薬を個人輸入代行サイトで購入すると薬機法55条違反に問われるおそれがあるため、この点を理解した上で選択しなければなりません。
正規の医療機関で受け取れば薬害救済制度の対象となり、重い副作用が生じた際に補償を請求できます。
医療サポートの有無
処方薬では定期診察により体重や肝腎機能を経過観察できるため、効果判定と副作用対策を同時に進められます。
対照的にサプリは自己判断で継続することが多く、体調変化を見落として代謝障害を招いた例が学会発表で取り上げられました。
さらに医療スタッフが用量調整や生活指導を行うと半年後の治療継続率が80%を超えたとのデータもあり、伴走型サポートが長期成功の鍵を握ります。
内科でもらえる痩せる薬についてよくある質問

内科でもらえる痩せる薬に関して、よくある質問を紹介します。
GLP‑1注射は内科で処方してもらえますか?
多くの一般内科では2型糖尿病治療の一環として、GLP‑1受容体作動薬(例:セマグルチド、リラグルチド)の注射を受けられます。
ただし、自由診療扱いになり、保険診療より費用が高くなる点に注意が必要です。
糖尿病専門医のいるクリニックでは用量調整や低血糖対策を含めたフォローが整っており、初回は血液検査や食事指導も合わせて行われる場合がほとんどです。
渡されるペン型製剤は週1回用と毎日用があり、保冷輸送後は2〜8℃で保存する決まりがあります。
保険適用になる条件は?
「食事療法・運動療法を行っても血糖が高い2型糖尿病」の場合に限られ、減量目的のみでは保険は使えません。
具体的には、経口薬など既存治療を一定期間行ってもHbA1cが目標を上回るときに追加処方が認められます。
2025年時点で肥満症(BMI30以上)のみを理由に保険が適用されるGLP‑1製剤はなく、肥満外来で使われるリラグルチド3 mg製剤も自費診療扱いです。
妊娠中でも使用できますか?
妊娠中と授乳期はGLP‑1注射を避けるべきだと添付文書に明記されています。
動物実験で胎児の骨格形成に影響が出た報告があるため、国内基準では「使用しないこと」が原則です。
妊娠を計画している場合は、医師がインスリンなど安全性の高い薬へ切り替えるよう調整します。
なお、万一服薬後に妊娠が判明したときは自己判断で中止せず、すぐに担当医へ連絡して経過観察を受けてください。
産後に再開する場合でも授乳終了を待ち、最低2か月の休薬期間を空けるよう求められます。
どれくらいで効果が出ますか?
食欲の抑制は投与開始から2〜4週で自覚する人が多く、国内試験では3か月時点で平均体重が3〜5%減っています。
用量を段階的に増やすため、半年続けると10%前後の減量が見込める一方、吐き気や便秘が強いと増量スケジュールを遅らせるケースもあります。
さらに、週1回製剤の場合は忘れず自己注射を続けることが結果に直結し、医師は毎回の診察で生活習慣の改善度も確認します。
体重が停滞したときは筋力トレーニングやたんぱく質摂取を見直すと、再び緩やかに減り始める例が少なくありません。
内科でもらえる痩せる薬まとめ
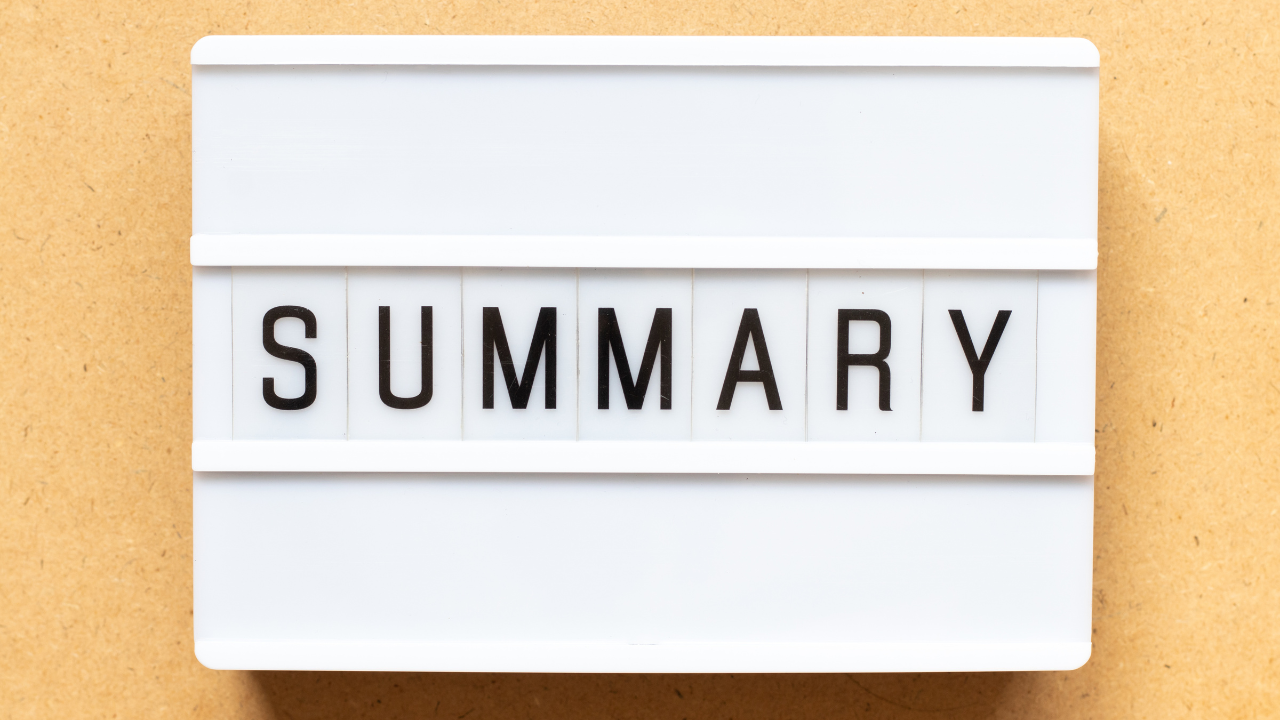
GLP‑1受容体作動薬は内科で血糖管理を目的に保険処方される一方、減量のみを狙う場合は自費診療となります。
保険適用には「食事・運動を行っても血糖目標に達しない2型糖尿病」であることが必須で、高度肥満症のみでは対象外です。
妊娠中や授乳期は使用できず、計画妊娠前は早めに医師へ相談して代替治療へ切り替える必要があります。
減量効果は開始後数週で表れ、半年ほどで体重の約1割が減る例が多いものの、継続注射と生活改善が前提です。
費用や安全面を踏まえ、診察時には「目的」「保険適用の可否」「副作用と対策」をしっかり確認してから治療を始めましょう。